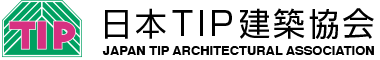TIPコラム
50年を超えたRCの箱 松川ボックス(宮脇壇、1971・1978)
2025.04.23
建築をつくることは、あらゆるものとの闘いです。土地の条件、法規制はもとより、多くの場合はコスト、ときには味方であるはずのクライアントともぶつかり合うこともざら。建築家は、こうしたハードルを乗り越えつつ、つくり続けるタフネゴシエーターであらねばなりません。建築家・宮脇壇が、本作品を発表したのは35歳のとき。表現者として、クライアントの意向に反しても突っ走ることを卒業し、敷地条件、法規制とも折り合い取りつつ、都市の中でクライアントともに住宅をつくる方法論を模索し始めたときに生まれたもので、この作品は宮脇にとってエポックをなすのものです。


東京都新宿区にある、2階建ての住宅が密集する地域。だから、周辺の地域に合わせるのは当然のこと。家の全体のかたちが北側斜線や道路車線、容積率でほぼ決まってしまうのが現実です。そうした中で、外側のかたちをコンクリートの箱でつくり、その中に、可変性をもたせた木構造を組み合わせるのが、宮脇の「ボックスシリーズ」に共通した考え方です(宮脇はこれを「混構造」といいました)。本作品では、中庭を確保するために、容積を切り分けて本棟と附属屋の2棟を設け、その箱をV字型にカットすることで中庭空間をつくりました(宮脇によると、1971年の第1期の計画の時点で、旧母屋に第2期の増築計画も念頭にあったそうです。実際、1978年の第2期の増築により、中庭をもつコートハウスとなりました)。宮脇は、この作品によって、日本建築学会賞を受賞しています。





先日、松川ボックスを訪ねました。まず、公開されている第1期の母屋へ。無表情に見えるRCの箱の中に入ると、吹抜けのある居間へとみちびかれます。現在は、中庭を介してつながる付属屋がなくなったものの、トップライトをもつ吹抜けの威力か、内部に閉じ込めれたという感じはありません。1階は居間と食堂、和室、そしてキッチン・浴室、トイレの機能的なスペース、2階は夫婦と子供の部屋。思いの外、こじんまりとまとまったスペース。興味深いエピソードとして、宮脇は、クライアントのもっていた家具類を所員に譲らせ、あらためて宮脇自身が家具を選び直したといいます。どこまでも、おせっかいでクライアントの生活にも足を踏み入れてしまうのが建築家の性(さが)というところです。手間暇のかかるわりに、実入りの少ないのが住宅設計だといわれますが、施工現場、コンクリート打放しの現場に出かけ、作業服を着てともに参加していたころの宮脇の作品です。内部の木構造でつくられた部分、建具類はほぼ竣工時のまま。これも、クライアントに好まれたからです。50年以上前のRCの箱は、今なお健在だという印象をもちました。(鈴木洋美)