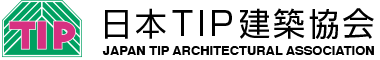TIPコラム
大屋根のもとにつつまれたアトリエ併用住宅 世田谷美術館分館・向井潤吉アトリエ館
2024.07.22

東京を代表する住宅地となった世田谷区。ところが、かつては周りに畑が広がる村でした。そこに芸術家たちの集う村づくりの夢を共有するかたちで、建築家・菅原栄蔵にさそわれて画家・向井潤吉は、世田谷区弦巻町へと引っ越します。それが、1933年のとき。1930年にフランスでの画家修行を終え、精力的に作品を発表し、画壇での知名度も少しずつ上がりはじめたころでした。最初は、菅原のアトリエを譲り受け、後に菅原の設計によって居宅を構えることになります。芸術家村の構想は実現しなかったものの、そこで向井が発見したものが、世田谷を含む武蔵野の自然でした。

民家との出会いは、向井の戦争体験として、切り離せません。向井も他の洋画家と同様に、戦時体制のもとに組み込まれていくこととなります。日本軍のプロパガンダとしての大画面の作戦記録画として数々の作品を残しますが、日本の敗戦を迎えたとき、そのポカリと空いた空白を埋めたものが民家でした。敗戦間際、手元にあった、柳田國男、今和次郎らがまとめた『民家図集』(1931年)を手にしたこともきっかけとなりました。向井の民家への最初の取組みが、疎開していた長女を迎えに行った際に訪れた新潟県北魚沼郡川口村を描いた「雨」という作品でした。

その後、向井潤吉に大きな転機が訪れます。1961年、不審火によるアトリエと応接間の焼失という事態です。手元にあった100点を超える作品と資料を、向井は失うことになるのですが、かえってそれをバネに民家を中心とした作家活動を繰り広げ、その後30年、90歳を超えるまで描き続けることとなります。ところでその後、向井が再建したアトリエ併用住宅は、民家風の大屋根のもとに、吹き抜け空間をもつアトリエ、その一画に設けた炉のある和室、妻のための和室(妻の和室は、現在玄関ホールへと改装されています)、そして家族のための生活空間がしつらえられました。向井邸の特徴は、民家を思わせる大ぶりの部材の使用です。柱や梁には太くたくましい部材が使われていますが、吹抜け空間を支える合理的な使い方をされていることに目が行きます。


最後に、「民家の向井」といわれるふさわしいエピソード。1969年、岩手県一ノ関の旅館にある土蔵が、国体のために取り壊されることを知り、向井は土蔵を丸ごと譲り受け、12トントラック2台分の解体部材を自宅に運びこんだものの、使えたのは2本の梁と1本の棟木と瓦の一部のみ。とはいえ、この蔵は、元のアトリエと廊下でつながれ、新たな向井のアトリエとなります。いかにも、民家の向井にふさわしいアトリエ空間が生まれ、これが現在の向井潤吉アトリエ館となりました。(鈴木洋美)